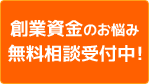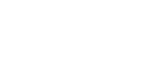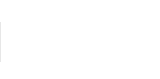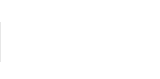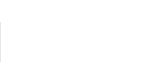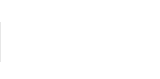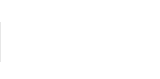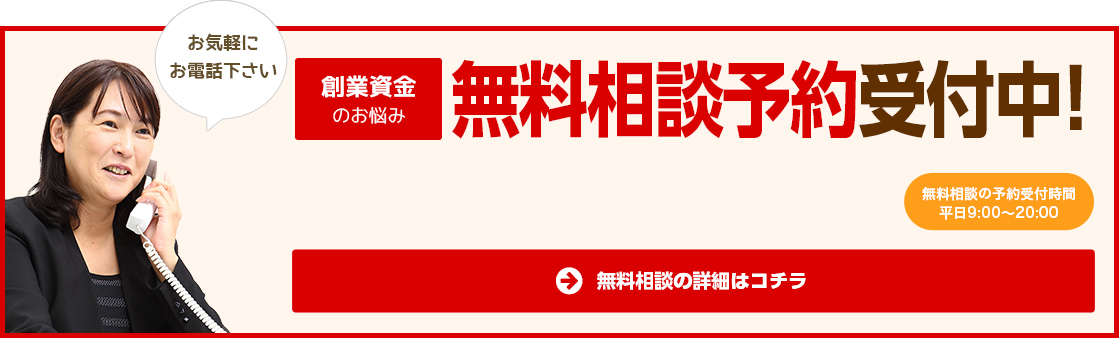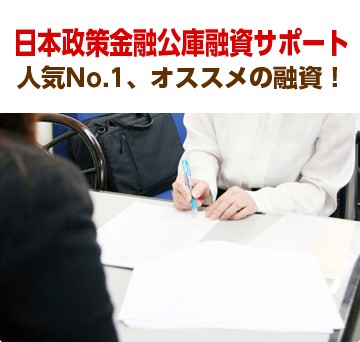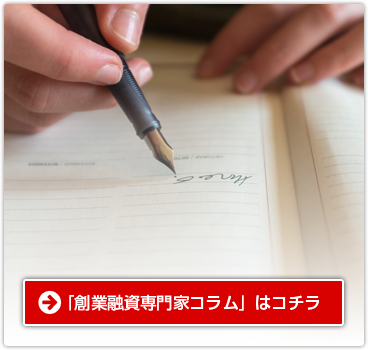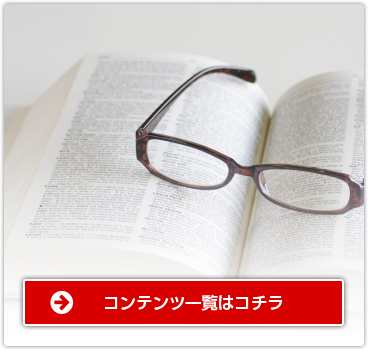日本政策金融公庫の融資は誰でも使える?〜創業者・既存企業の違いと活用ポイント〜
投稿日:2025年5月21日
さいたま市浦和で創業の方を応援しています!埼玉 創業融資サポートセンターです。
「日本政策金融公庫の融資は誰でも使えるの?」というご質問をよくいただきます。
結論から言えば、原則として、創業予定者から既存企業まで幅広く利用可能です。ただし、制度の目的や審査ポイントには違いがあり、利用者の立場によって注意すべき点が変わってきます。
今回は、創業者と既存企業の違いを踏まえて、日本政策金融公庫の融資をうまく活用するためのポイントを詳しく解説します。

日本政策金融公庫とは?
日本政策金融公庫(通称:日本公庫)は、国が100%出資する政策金融機関です。
民間金融機関では対応が難しい創業間もない企業や小規模事業者、中小企業に対して、事業活動に必要な資金を貸し出す役割を担っています。
景気対策や雇用創出、地域経済の活性化など、政策的な目的を背景に設けられているため、低金利・長期返済・無担保融資といった条件で利用できる場合があるのが大きな特徴です。
日本政策金融公庫HP:https://www.jfc.go.jp/
創業者向け融資の特徴
創業予定者や開業から間もない事業者にとって、日本政策金融公庫はとても心強い存在です。
代表的な制度としては「新規開業・スタートアップ支援資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」などがあり、無担保・無保証で融資が受けられるケースもあります。
このような制度は、創業期の事業者にとって、金融機関からの融資を受けにくい状況を補う目的で設計されています。
したがって、創業者にとっては非常に利用価値の高い資金調達手段と言えるでしょう。
ただし、以下のような点が特に審査対象となりますので覚えておきましょう。
自己資金の有無と蓄積方法
創業者が融資を利用するには、希望融資額の10分の1以上の自己資金を準備していることが望ましいとされています。
つまり、1000万円の資金が必要であれば、100万円以上の自己資金を用意しておくことが求められます。
また、その資金が「計画的に貯めたものであるか」が重視されます。
この自己資金は、単なる預金残高だけでなく、開業準備に使った支払い(店舗契約、機器購入等)も一部含めて計上できるケースがありますので、申込時に確認しておきましょう。
※令和6年3月31日に新創業融資制度の廃止にともない、10分の1以上の自己資金要件はなくなりました。しかし、自己資金は審査のうえでも重要な要素のひとつとなりますので、融資成功のためにはしっかりと用意する必要があります。
過去の職務経験やスキル
創業しようとする分野での経験があるかどうか、業界知識がどの程度あるかも判断材料となります。
創業者の場合、まだ売上実績がない状態での申請となるため、過去の事業経験や事業に対する理解度などが評価のカギになります。
飲食店であれば調理師や店舗運営の経験、美容室なら業界歴などがプラス要素になります。
事業計画の現実性と数字の根拠
融資審査では、創業動機、提供する商品やサービス、ターゲット市場、競合との差別化、収支見通しなどを記載した「創業計画書」が重要視されます。
担当者は、この計画に現実性や実行力があるかを見極めており、単に夢や熱意を書くのではなく、具体的な数字や市場分析が求められます。
これらを踏まえた上で準備することで、創業者でも十分に融資のチャンスがあります。
既存企業向け融資の特徴
すでに事業を営んでいる法人や個人事業主であれば、創業者向け以外にもさまざまな制度を利用することができます。
たとえば「一般貸付」や「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」などが該当し、用途に応じた幅広い資金調達が可能です。
既存企業の場合は、実績や帳簿・決算書などの数値がある分、定量的な評価が可能となります。
特にチェックされるのは以下の点です。
直近の決算内容(売上・利益・借入残高など)
利益が出ていなくても、改善傾向や財務の健全性が評価されることもあります。
既存企業では、決算書や確定申告書の内容が審査の中心となります。
過去2~3年分の売上、利益、借入状況、自己資本などが重視されます。
赤字決算が続いていたり、債務超過の状態にあると審査は厳しくなります。
黒字化に転じているなどの改善傾向があれば、それを説明できる資料やコメントを添えると良いでしょう。
税金の支払い状況・借入金の返済状況
税金の滞納があると融資審査にはマイナス評価になります。
融資申請前に未納がある場合は、分納計画を立てて支払いを開始していることを証明できれば、一定の配慮が得られる場合もあります。
また、他金融機関からの借入状況や返済状況もチェックされるため、日頃から資金管理をしっかり行っておくことが大切です。
必要資金の使途と返済計画の明確さ
資金を何に使うか、どう回収して返済していくかが具体的に説明できることが求められます。
漠然とした「資金繰りのため」では通りにくく、「設備の導入によって売上がこれだけ伸びる見込み」「仕入れ増加に対応するための運転資金」など、具体的な説明が必要です。
一方で、売上減少や経営悪化などの要因がある場合でも、その原因と今後の改善策を論理的に説明できれば、前向きに評価されるケースもあります。
利用の際のポイントと注意点
創業者・既存企業のいずれにしても、以下のポイントを押さえることで、融資の通過率を高めることができます。
専門家の支援を活用する
商工会議所や中小企業診断士、税理士などに相談することで、計画書の作成支援や面談対策が受けられます。
とくに「特定創業支援等事業」の対象になれば、創業時の金利がおさえられるなどのメリットもあります。
○こちらの記事もおすすめ>>>「特定創業支援等事業とは?創業を目指す方が活用すべき支援制度」
資金調達スケジュールの余裕を持つ
日本公庫の融資は、書類提出から実行まで1か月前後かかることが一般的です。
急な資金ニーズに対応するには不向きな場合もあるため、資金が必要になる2~3か月前から準備を始めるのが理想です。
面談の受け答えも重要
融資申請後には、公庫担当者との面談があります。創業者の場合は必ずありますし、既存企業でも初めての借入の場合は面談があることがほとんどです。
ここでは、計画書に書いてある内容を自分の言葉で説明できるかどうか、経営者としての考え方、リスクへの備えなどが見られています。
「なぜ今その事業をやるのか」「競合と何が違うのか」「利益はいつから出そうと考えているのか」といった質問に答えられるように準備しておきましょう。
○こちら記事もあわせてどうぞ!>>>「日本政策金融公庫の面談はどんな質問をされるのか」
まとめ
日本政策金融公庫の融資制度は、創業者から既存企業まで幅広い層に対応していますが、それぞれに求められる視点や準備内容は異なります。
創業者であれば、自己資金や事業経験、現実的な計画の準備が鍵となります。一方、既存企業であれば、決算の健全性や納税状況、改善計画の具体性が重要視されます。
融資は単なる「お金を借りる行為」ではなく、経営計画を見直す好機でもあります。
専門家のサポートを受けながら、しっかりと準備を整えれば事業の大きな推進力になります。ぜひ積極的に活用を検討してみてください。
埼玉創業融資サポートセンターおすすめサービス>>>創業融資無料診断
埼玉 創業融資サポートセンターはさいたま市浦和区/浦和駅徒歩5分/銀行対応に強い税理士
メールでのお問い合わせはこちら>>>【お問い合わせフォーム】
お電話はこちら>>>フリーダイヤル:0120-814-610(平日9時~18時)
創業融資専門家コラムの最新記事
- 創業融資はひとりで進める?税理士サポートを検討するタイミング
- 創業融資は審査通過・融資獲得がゴールではない|計画書の重要性
- 創業融資が返済できない。どうしよう・・・|早めの相談が未来を守る
- 創業融資が通らない理由は「計画」よりも「人」?
- 【最新版】CIC信用情報の見方|開示報告書はここをチェック!
- 預金通帳を日本政策金融公庫の創業融資面談で確認されるのは何故
- 創業1期目が赤字でも公庫融資は受けられるのか?現実と可能性を冷静に見つめる
- 【日本政策金融公庫】融資の入金先はどこが良いか?ネット銀行はあり?
- 日本政策金融公庫の創業融資とブラックリストの影響
- 創業融資の気になる金利「創業後目標達成型金利」について知ろう
- 税金の滞納が融資審査に与える影響と資金調達対策
- 特定創業支援等事業とは?創業を目指す方が活用すべき支援制度
- 返済期間が事業に与える影響とは? 創業資金で知っておきたい基礎知識
- 「新創業融資制度」は廃止!そのかわり「新規開業資金」の活用を!
- 日本政策金融公庫の創業融資はいくらまで受けられますか?
- 日本政策金融公庫は借換に対応しているのか解説します
- 「固定金利」とは|日本政策金融公庫の金利は固定金利
- 日本政策金融公庫の創業融資申込のポイント・気をつけること
- 日本公庫オンラインのサービスはご存じですか?【日本公庫ダイレクト】
- 日本政策金融公庫の融資面談時の服装はどのような恰好が良い?
- 日本政策金融公庫の創業融資申込で必要書類は?◆さいたまの税理士がサポート
- 日本政策金融公庫の融資審査を通す!創業計画書の書き方のコツ
- 日本政策金融公庫の融資審査はCICを利用するのは何故
- 日本政策金融公庫の融資審査の期間はどれくらいかかるの?
- 創業融資は日本政策金融公庫に申込む。そこにメリットはあるのか?
- 創業融資の申込でしてはいけない・注意点・NGポイント
- 日本政策金融公庫で融資を申し込みたい!相談どこにする?
- 日本政策金融公庫で融資の申込:審査に落ちる理由を知ろう
- 日本政策金融公庫で借りたら団体信用生命保険を案内された
- 日本政策金融公庫の面談はどんな質問をされるのか
- 消費者金融で借金があるけど日本政策金融公庫の融資審査は通る?
- 金利が知りたい|日本政策金融公庫の創業融資
- 日本政策金融公庫の創業融資は何回申請ができる?追加融資についても解説
- 経験なしで<日本政策金融公庫>創業融資を受けたい方へ
- 創業計画書の売上予測の方法について
- 創業融資で1,000万の借入は可能なのか!?
- 創業融資は返済不要という噂は真実か
- 創業計画書の運転資金|いくら?どうやって書く?
- 日本政策金融公庫のインターネット申し込み~準備と注意点
- 創業計画書の設備資金は何を書くのか
- 【起業するなら】創業融資を受けた方が良い4つの理由
- 創業融資の難易度が知りたい|日本政策金融公庫の場合
- 創業融資における創業計画書の重要性
- 創業してすぐ融資を受けたい!どこが良い?
- 気をつけるべき創業融資の失敗例
- 日本政策金融公庫の創業融資を税理士に依頼するメリットとポイント
- 日本政策金融公庫「新規開業資金」の拡充について
- 法人と個人事業主~融資審査に有利不利はあるのか
- 自己資金はタンス預金!創業融資では認められるのか
- 創業融資、まず何を準備すべきかポイントを教えます
- 創業融資制度は何年目までに申し込みが必要ですか?
- 日本政策金融公庫に融資の相談をしたいなら
- 専門家に頼むメリット~会社設立編~
- 青色申告承認申請書を提出するタイミング=開業届と一緒でOK
- 創業融資を申込むとき、商圏調査は必要か?
- 自己資金の定義とは。家族から借りたお金は?もらったお金は?
- 日本政策金融公庫の据置期間について
- 日本政策金融公庫「創業融資」の手続きの流れ
- 個人再生が日本政策金融公庫の融資に与える影響
- 起業時の注目資金調達「新創業融資制度」|日本政策金融公庫の融資
- プロパー融資を受けるのは難しいのはなぜか
- 創業融資での自己資金の重要性
- 日本政策金融公庫の融資|審査が甘いのは本当か
- 【事例/物販】日本政策金融公庫に創業融資を申し込む
- 日本政策金融公庫は土曜日も電話相談ができる
- 日本政策金融公庫の生活衛生貸付とは
- 創業融資を申し込むタイミングはあるのか
- コロナ禍での創業融資~日本政策金融公庫の現状
- 日本政策金融公庫、浦和支店とさいたま支店
- フランチャイズ加盟で日本政策金融公庫の融資に申し込む場合
- 創業融資を日本政策金融公庫で受けた方がいい理由◆さいたまの税理士がサポート
- 日本政策金融公庫で融資の申込:審査にかかる期間◆さいたまの税理士がサポート
- 日本政策金融公庫の創業融資:申込前のチェック◆さいたまの税理士がサポート
- 日本政策金融公庫で創業融資申込:自己資金について◆さいたまの税理士がサポート
- 【埼玉】日本政策金融公庫の再挑戦支援資金融資ご存知ですか?
- 公庫【女性・若者/シニア起業家支援資金】の融資申請なら埼玉創業融資サポートセンターへご相談ください
- 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」のメリットとは?
- 日本政策金融公庫の創業計画書の書き方 〜その4(全4回)〜
- 日本政策金融公庫の創業計画書の書き方 〜その3(全4回)〜
- 日本政策金融公庫の創業計画書の書き方 〜その2(全4回)〜
- 日本政策金融公庫の創業計画書の書き方 〜その1(全4回)〜
- 日本政策金融公庫で融資を受けるための流れについて!
- 埼玉県の創業融資の専門家がサポート【埼玉創業融資サポートセンターなら初回面談無料】
- 起業時に利用できる、日本政策金融公庫の融資制度について
- 税理士・社労士は得意分野が人それぞれ異なります
- すべての税理士が資金調達に詳しいわけではない!
- 融資申請で銀行が嫌う勘定項目について
- 銀行からの評価を下げる決算書とは?
- 銀行からの融資は格付けだけで決まるのか?
- 金融機関(銀行)の種類と役割について知ろう!
- 創業融資には欠かせない!事業計画書(創業計画書)の作成のポイント!
- 日本政策金融公庫の融資を受ける基礎知識【事業計画書は減点方式】
- 創業融資に詳しい税理士に相談して「創業融資制度」を賢く使う!
- 創業融資は日本政策金融公庫を活用しよう!起業時にオススメ!
- 日本政策金融公庫で審査を通す確率をアップするコツ
- さいたま市で起業する方の創業融資相談なら【埼玉創業融資サポートセンター】
- 無担保・無保証!日本政策金融公庫を活用しよう!
- 「創業融資専門家コラム」始めました!